キャンプで地面に直接マットを敷いて寝ると、石のゴツゴツ感や地面の冷たさが気になって、朝まで熟睡できなかった経験はありませんか。そんな悩みを解決してくれるのがコットです。地面から浮いた状態で寝られる簡易ベッドのようなアイテムで、一度使うと手放せなくなるキャンパーも多いんです。
ただ、いざコットを選ぼうとすると、ヘリノックス、コールマン、DOD、WAQなど、たくさんのブランドから様々なモデルが出ていて、どれを選んだらいいのか本当に迷います。ハイコットとローコットの違いって何なのか、組み立ては難しくないのか、重さはどのくらいが妥当なのかなど、初めて購入する時には分からないことだらけですよね。
この記事では、キャンプ歴5年の私が実際に複数のコットを使ってみて分かった、本当に使いやすいコットの選び方をお伝えします。値段だけで選んで失敗したくない方、自分のキャンプスタイルに合ったコットを見つけたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
コットって本当に必要なの?使う意味を知ろう
まず、コットがどんなものか、そしてなぜ多くのキャンパーが使っているのかを理解しておきましょう。コットとは、脚が付いた折りたたみ式の簡易ベッドのことです。キャンプマットと違って地面から離れた位置で寝られるので、様々なメリットがあります。
地面のコンディションに左右されない快適さ
キャンプ場の地面は、思っている以上に寝づらいものです。テントを張る場所によっては、小石や木の根っこがあったり、雨上がりで湿っていたりすることもあります。マットだけだと、こうした地面の状態がダイレクトに伝わってきて、寝心地が悪くなってしまいます。


コットを使えば、地面の状態を気にせず快適に眠れます。整地されていない場所でも、フラットな寝床を確保できるのが最大のメリットです。
季節ごとの温度変化から体を守ってくれる
地面は、思っている以上に体温を奪います。特に秋から冬にかけてのキャンプでは、地面からの冷気で背中が冷えて眠れないことも少なくありません。逆に夏場は、地面の熱気がこもって蒸し暑く感じることもあります。
コットを使うと、地面との間に空間ができるため、底冷えや地熱の影響を受けにくくなります。夏は地面との間を風が通り抜けて涼しく、冬はその空間が断熱層の役割を果たしてくれます。もちろん、冬キャンプではコットの上にマットを重ねることで、さらに保温性を高めることができます。
設営の手間を減らせて荷物置きにも使える
コットのもう一つの魅力は、多用途に使えることです。寝る時だけでなく、昼間はベンチ代わりにもなりますし、荷物置き場としても活躍します。地面が濡れている時でも、コットの上に荷物を置いておけば濡れる心配がありません。
グランドシートやインナーテントを使わなくても寝られるので、フロアレステントでキャンプをする人には特におすすめです。準備にかかる時間も短縮できて、撤収も楽になります。
ただし、コットにもデメリットがあります。組み立てに多少時間がかかることと、マットに比べるとサイズが大きく重いことです。特にソロキャンプや徒歩・バイクでのキャンプでは、この重さとサイズがネックになることもあります。
ハイコットとローコットの違いを理解する
コットを選ぶ上で最初に決めなければいけないのが、ハイコットにするかローコットにするかです。それぞれに特徴があるので、自分のキャンプスタイルに合わせて選びましょう。
ローコットは軽量コンパクトで狭いテントでも使える
ローコットは、地面から15センチから20センチ程度の高さのコットです。現在のキャンプシーンでは、このローコットが主流になっています。
ローコットの最大のメリットは、軽量でコンパクトなことです。ハイコットに比べて脚部のパーツが短く軽量なので、持ち運びの負担が少なくて済みます。また、高さが低いので、天井の低いテントでも圧迫感なく使えます。
ただし、ローコットにもデメリットがあります。高さが低いため、立ち座りする時に腰に負担がかかることと、コットの下に荷物を収納しにくいことです。また、ハイコットに比べると地面からの影響を受けやすくなります。
ハイコットは立ち座りが楽でベンチ代わりにも使える
ハイコットは、地面から30センチから40センチ程度の高さがあるコットです。椅子に近い高さなので、立ち座りがとても楽にできます。
ハイコットの魅力は、その多用途性です。昼間はベンチやチェア代わりに使えて、夜は快適なベッドとして機能します。コットの下には十分なスペースがあるので、靴やバッグなどの荷物を収納できて、テント内を整理整頓しやすくなります。
また、地面からの距離があるため、底冷えや地熱の影響をローコットよりも受けにくいというメリットもあります。雨が降った時も、地面からの湿気の影響が少なくて済みます。


ハイコットは、ファミリーキャンプやオートキャンプなど、荷物の重さをあまり気にしなくていい場合におすすめです。立ち座りが楽なので、腰や膝に不安がある方にも向いています。
迷ったら2WAYコットが便利
ハイコットとローコット、どちらにするか迷ったら、2WAYコットを検討してみてください。2WAYコットは、脚部の付け方を変えることで、ハイスタイルとロースタイルの両方で使えるコットです。
2WAYコットのメリットは、その汎用性の高さです。広いテントや開放的な場所ではハイスタイル、狭いテントや低い天井のタープ下ではロースタイルというように、シーンに合わせて使い分けられます。
初めてコットを購入する方には、2WAYコットが特におすすめです。キャンプスタイルが変わっても長く使い続けられますし、一台で両方の良さを体験できます。価格は通常のコットより少し高めですが、その分の価値は十分にあります。
ただし、2WAYコットは構造上、専用のハイコットやローコットに比べると、若干重くなる傾向があります。とはいえ、重量は3キロ前後のものが多く、許容範囲内といえるでしょう。
寝心地を左右する3つの重要ポイント
コットの寝心地は、主に3つの要素で決まります。横幅の広さ、生地の張りの強さ、そして軋み音の大きさです。これらをしっかりチェックすることで、快適に眠れるコットを選べます。
横幅は最低でも65センチ以上を選ぶ
コットの横幅は、寝心地に直結する最も重要な要素です。多くのコットは幅が60センチから65センチ程度ですが、この幅だと人によっては窮屈に感じることがあります。
実際に寝転んでみると分かりますが、60センチ以下の幅だと、寝返りを打つ時に肩や腕がコットからはみ出してしまうことがあります。寝ている間に何度も寝返りを打つことを考えると、最低でも65センチ以上、できれば70センチ以上の横幅があると快適です。
ワイドコットの中には、幅が100センチを超えるモデルもあります。こうした超ワイドモデルは、二人で寝ることも可能で、ファミリーキャンプでも活躍します。ただし、重量とサイズが大きくなるので、車での移動が必須になります。
生地の張りが強いと体が沈み込まない
コットの生地の張り具合も、寝心地に大きく影響します。張りが弱いと体が沈み込んでしまい、腰や背中に負担がかかります。逆に、張りが強すぎると硬く感じて、体のあちこちが痛くなることもあります。
理想的なのは、適度な反発力がある張りです。体を預けた時に少しだけ沈み込み、体の曲線に合わせてフィットしてくれる程度がちょうどいいです。


生地の素材も重要です。600デニール以上のオックスフォード生地やポリエステル生地を使っているコットは、耐久性が高く張りも適度にあることが多いです。安価なコットだと、生地が薄くて張りが弱いものもあるので注意が必要です。
また、コットの上にマットを敷くことで、張りの弱さをカバーすることもできます。特に冬キャンプでは保温性も上がるので、マットとの併用をおすすめします。
軋み音が小さいモデルを選ぶと快眠できる
意外と見落としがちなのが、コットの軋み音です。寝返りを打つたびにギシギシと音がすると、自分だけでなく周りの人の睡眠も妨げてしまいます。
軋み音の原因は、主に2つあります。一つは、フレームと生地の摩擦音。もう一つは、脚部のジョイント部分がこすれる音です。高品質なコットは、これらの接合部に滑りやすい素材を使ったり、精度の高い加工をしたりすることで、軋み音を抑えています。
軋み音を減らす工夫として、組み立て時にフレームと生地の間にスリップ生地を挟んでいるモデルもあります。こうした設計のコットは、多少価格が高くても、静かで快適な睡眠が得られるので、検討する価値があります。
組み立てやすさで選ぶコットの設営タイプ
コットの組み立て方には、大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれに特徴があるので、自分がどれくらい組み立ての手間をかけられるかで選びましょう。
折りたたみ式は展開するだけで設営完了
折りたたみ式は、最も簡単に設営できるタイプです。フレームと脚部が一体化しているので、パーツを組み立てる必要がありません。収納状態から広げて、ロックをかければ設営完了です。
組み立てにかかる時間は、わずか1分から2分程度。力も必要ないので、女性や子供でも簡単に扱えます。キャンプ初心者や、設営にあまり時間をかけたくない方におすすめのタイプです。
折りたたみ式のデメリットは、収納サイズが大きくなることです。フレームが一体化しているため、折りたたんでもある程度の長さが残ります。車のトランクに入れる時は、このサイズをしっかり確認しておきましょう。
また、折りたたみ式は他のタイプに比べて重量が重くなる傾向があります。5キロから7キロ程度のものが多いので、持ち運びには少し苦労するかもしれません。オートキャンプや、設営場所が近い場合に向いています。
組み立て式はコンパクトだが力が必要
組み立て式は、フレーム、生地、脚部が別々になっているタイプです。フレームを生地に通して、脚部を取り付けることで組み立てます。
組み立て式のメリットは、パーツを分解できるので、収納時に非常にコンパクトになることです。重量も2キロから3キロ程度と軽量なモデルが多く、持ち運びやすさを重視する方に向いています。
ただし、組み立てには少しコツと力が必要です。特に、脚部をフレームに取り付ける時には、かなり強い力で押し込まなければいけないモデルもあります。慣れれば5分から10分で組み立てられますが、初めての時は苦労するかもしれません。
組み立て式のもう一つのポイントは、フレームの連結方法です。ショックコードでフレームが連結されているタイプは、バラバラにならないので組み立てやすいです。逆に、フレームが完全に分離するタイプは、組み立て順序を間違えやすいので注意が必要です。
ジッパー式は力要らずで組み立てられる
ジッパー式は、比較的新しいタイプのコットです。フレームと脚部は一体化していて、本体を広げた後にジッパーを閉じるだけで設営が完了します。
折りたたみ式の簡単さと、組み立て式のコンパクトさを兼ね備えたようなタイプで、力もあまり必要ありません。初心者や力に自信がない方でも、ストレスなく組み立てられます。
ジッパー式は、まだ製品数が少ないタイプですが、組み立てやすさと使いやすさのバランスが良いので、今後人気が出てくると予想されます。見つけたら、ぜひ検討してみてください。
ただし、ジッパーが壊れると使えなくなるというリスクがあります。ジッパーは消耗品なので、長期間使っているうちに動きが悪くなることもあります。定期的にジッパーのメンテナンスをすることが大切です。
持ち運びやすさを決める重量とサイズ
コットの持ち運びやすさは、主に重量と収納サイズで決まります。自分のキャンプスタイルに合わせて、適切な重さとサイズを選びましょう。
重量は2.5キロ以下が理想的
コットの重量は、持ち運びやすさに直結する重要な要素です。キャンプは荷物が多くなるので、コットはできるだけ軽い方がいいのは間違いありません。
目安としては、2.5キロ以下なら軽量、3キロから4キロなら標準、4キロ以上は重めと考えてください。2.5キロ以下のコットなら、車からの荷下ろしや、サイトまでの移動も比較的楽にできます。


バイクキャンプや登山でのテント泊を考えている方は、2キロ前後の超軽量モデルを選ぶ必要があります。ただし、超軽量モデルは価格が高めで、寝心地や耐久性が犠牲になることもあるので、バランスを考えて選びましょう。
逆に、オートキャンプで車をサイトに横付けできる場合は、重量はあまり気にしなくても大丈夫です。4キロから5キロのコットでも、キャリーカートを使えばスムーズに運べます。寝心地や組み立てやすさを優先して選びましょう。
収納サイズは車のトランクに入るか確認
重量だけでなく、収納サイズも重要です。いくら軽くても、収納サイズが大きすぎると、車のトランクに入らなかったり、他の荷物を圧迫したりします。
一般的なコットの収納サイズは、長さ50センチから60センチ、幅15センチから20センチ、高さ15センチから20センチ程度です。この程度のサイズなら、普通車のトランクにも問題なく積めます。
折りたたみ式のハイコットは、収納時でも長さが80センチから120センチになることがあります。こうした大型のコットは、軽自動車や小型車だとトランクに入らないこともあるので、事前にサイズをしっかり確認しましょう。
素材と耐荷重で長く使えるコットを選ぶ
コットを長く使い続けるためには、フレームや生地の素材、そして耐荷重もチェックしておく必要があります。安価なモデルだと、すぐに壊れてしまうこともあるので注意が必要です。
フレームはアルミ合金がおすすめ
コットのフレームには、主にアルミ合金、ステンレス、スチールが使われています。それぞれに特徴があるので、用途に合わせて選びましょう。
アルミ合金は、強度と軽さのバランスが最も優れている素材です。錆びにくく、持ち運びやすいので、キャンプ用コットの主流になっています。特に、A7075アルミ合金という超々ジュラルミンは、航空機にも使われる高強度の素材で、軽量なのに頑丈です。
初めてコットを購入する方には、アルミ合金フレームのモデルをおすすめします。価格と性能のバランスが良く、長く使い続けられる耐久性があります。
ステンレスやスチールのフレームは、アルミよりも重いですが、価格が安いのがメリットです。重量を気にしないオートキャンプや、予算を抑えたい方に向いています。ただし、錆びやすいので、使用後はしっかり乾かして保管することが大切です。
木製フレームのコットもあります。ブナの木などを使った木製フレームは、温もりがあってキャンプサイトの雰囲気が良くなります。ただし、重量が重く、価格も高めなので、こだわりのある方向けの選択肢といえます。
生地は600デニール以上が理想
コットの生地は、寝心地だけでなく耐久性にも影響します。生地の厚さや強度を表す単位として、デニール数というものがあります。
デニール数が高いほど、生地が厚くて丈夫になります。キャンプ用コットの場合、600デニール以上の生地を使っているモデルが理想的です。反発力が強く沈みにくいうえ、破れにくくて長持ちします。
安価なコットだと、300デニールや400デニールの薄い生地を使っていることもあります。こうしたコットは、最初は問題なく使えても、すぐに生地が伸びたり破れたりする可能性が高いので、避けた方が無難です。
耐荷重は100キロ以上を選ぶと安心
コットの耐荷重も重要なチェックポイントです。耐荷重とは、コットが安全に支えられる重さの上限のことです。
一人で寝るだけなら、耐荷重80キロでも問題ないように思えますが、実際にはもっと余裕を持たせた方が安全です。寝返りを打つ時や、ベンチとして座る時には、瞬間的に体重以上の荷重がかかることがあります。
耐荷重は、フレームの素材や構造、脚部の数などで変わってきます。脚部が多いコットほど、荷重が分散されて耐荷重が高くなる傾向があります。ただし、脚部が多いと組み立てに時間がかかるので、バランスを考えて選びましょう。
あると便利な機能をチェックする
コットの基本性能以外にも、あると便利な機能がいくつかあります。こうした細かな機能の有無で、使い勝手が大きく変わることもあるので、チェックしておきましょう。
サイドポケットがあると小物の収納に便利
コットの側面にポケットが付いているモデルがあります。このサイドポケットが意外と便利で、スマホや眼鏡、時計などの小物を入れておけます。
寝る前にポケットに入れておけば、夜中にトイレに起きた時でも、すぐに懐中電灯やスマホを取り出せます。また、貴重品を入れておけば、盗難のリスクも減らせます。
サイドポケットは、テント内での生活を快適にする重要な機能です。コットを選ぶ際は、ポケットの有無と、ポケットの大きさもチェックしておくことをおすすめします。
ポケットの素材や作りも重要です。メッシュ素材のポケットなら、中身が見えて取り出しやすいです。防水素材のポケットなら、朝露や結露から貴重品を守れます。自分がどんなものを入れたいかを考えて選びましょう。
カラビナループで空間を有効活用
コットの側面にカラビナループが付いているモデルもあります。このループにカラビナを引っ掛けることで、ランタンや小物袋などを吊るせます。
テント内は限られたスペースなので、縦の空間を有効活用できるのは大きなメリットです。地面に置きたくないものや、取り出しやすい位置に置きたいものを吊るしておくと便利です。


収納袋が付属しているか確認
ほとんどのコットには収納袋が付属していますが、稀に別売りのこともあります。収納袋がないと、持ち運びや保管が不便なので、必ず付属品を確認しましょう。
収納袋の質も重要です。薄いナイロン製の袋だと、すぐに破れてしまうことがあります。厚手の生地で、しっかりした縫製の収納袋なら、長く使い続けられます。
メッシュ生地なら通気性が良い
コットの生地がメッシュ素材になっているモデルもあります。メッシュ生地は通気性に優れているので、夏のキャンプでは蒸れにくくて快適です。
ただし、メッシュ生地だと冬は寒く感じることがあります。オールシーズン使いたい場合は、通常の生地のコットを選んで、夏場は上にタオルを敷くなどの工夫をした方が良いかもしれません。
実際に使って分かったコットのコツ
ここまで選び方について説明してきましたが、実際にコットを使う上での注意点やコツもお伝えしておきます。知っておくと、より快適にコットを使えます。
初回の組み立ては時間がかかることを覚悟する
どんなに組み立てやすいコットでも、初めて組み立てる時は思った以上に時間がかかります。これは仕方のないことなので、焦らずゆっくり組み立てましょう。
説明書をよく読んで、手順を確認してから組み立て始めることが大切です。YouTubeなどで組み立て動画を探して見ておくと、さらにスムーズに組み立てられます。
購入後は、自宅で一度組み立て練習をしておくことを強くおすすめします。キャンプ場で初めて組み立てようとして、手間取って暗くなってしまった、という失敗談はよく聞きます。
2回目以降は、慣れてくるので組み立て時間が短くなります。最初は10分以上かかったコットも、慣れれば3分から5分で組み立てられるようになります。
テントの床を保護する工夫をする
コットの脚は、接地面が点になるため、テントの床に負荷がかかります。特にインナーテント付きのテントでコットを使うと、床生地が擦れて穴が開いてしまうことがあります。
この問題を防ぐには、コットの脚の下にラグや銀マットを敷くのが効果的です。専用の脚キャップも売られているので、それを使うとさらに安心です。
冬は下からの冷気対策が必須
コットを使うと地面からの底冷えは軽減されますが、冬キャンプではコットの下を通る冷気で寒く感じることがあります。これはコットの構造上、避けられない問題です。
対策としては、コットの上にマットを敷くことが効果的です。インフレータブルマットや銀マットを重ねることで、断熱性が高まります。また、コットの下に荷物を置いて、風の通り道を遮る方法も有効です。
定期的なメンテナンスで長持ちさせる
コットを長く使い続けるには、定期的なメンテナンスが必要です。使用後は、生地の汚れを拭き取り、しっかり乾かしてから収納しましょう。
フレームの連結部分やジョイント部分には、時々シリコンスプレーを吹きかけておくと、スムーズに動くようになります。また、生地が伸びてきたら、張りを調整できるモデルもあるので、説明書を確認してみてください。
予算別おすすめコットの選び方
コットの価格は、5千円程度の安価なものから、5万円以上する高級品まで幅広くあります。予算に応じて、どのようなコットを選べばいいかを解説します。
1万円以下のエントリーモデル
初めてコットを購入する方や、とりあえず試してみたい方には、1万円以下のエントリーモデルがおすすめです。この価格帯でも、基本的な機能は十分に備わっています。
ただし、安価なモデルは寝心地や耐久性が劣ることが多いです。生地が薄かったり、フレームの精度が低かったりするので、長期間使うことを考えると物足りなさを感じるかもしれません。


エントリーモデルは、年に数回しかキャンプに行かない方や、子供用として使う場合には十分です。ただし、本格的にキャンプを楽しみたい方は、もう少し予算を上げた方が満足度が高くなります。
1万円から2万円のミドルレンジ
1万円から2万円の価格帯は、コストパフォーマンスに優れたモデルが多く揃っています。寝心地、組み立てやすさ、持ち運びやすさのバランスが良く、多くのキャンパーにおすすめできる価格帯です。
この価格帯なら、有名ブランドのコットも選択肢に入ってきます。WAQ、DOD、コールマンなど、信頼できるブランドのコットが購入できます。
初めてコットを購入する方には、この1万円から2万円の価格帯がおすすめです。失敗のリスクが少なく、長く使い続けられる品質のコットが見つかります。
2WAYタイプや、ワイドタイプのコットもこの価格帯で購入できます。特に、国内メーカーのコットは、日本人の体格に合わせて設計されていることが多く、使いやすいのでおすすめです。
2万円以上のハイエンドモデル
2万円以上のハイエンドモデルは、寝心地や耐久性、デザイン性にこだわったコットです。ヘリノックスやスノーピークなどの高級ブランドのコットが、この価格帯に入ります。
ハイエンドモデルの魅力は、軽量なのに頑丈で、寝心地も抜群という点です。使用されている素材も高品質で、細部まで丁寧に作り込まれています。長期間使っても、ヘタリや壊れが少ないのも特徴です。
ハイエンドモデルを選ぶ時は、アフターサービスも確認しましょう。有名ブランドなら、パーツの交換や修理のサポートが受けられることが多く、長く愛用できます。
コットを使う時に一緒に揃えたいアイテム
コットを快適に使うためには、いくつかの関連アイテムも揃えておくと便利です。必須ではありませんが、あると快適さが格段に向上します。
キャンプマットで寝心地をさらに向上
コットの上にキャンプマットを敷くと、寝心地がさらに良くなります。特に、体圧を分散してくれるインフレータブルマットや、厚手のウレタンマットがおすすめです。
マットを敷くことで、コットの生地の張りが気にならなくなりますし、保温性も高まります。冬キャンプでは必須のアイテムといえるでしょう。
マットを選ぶ時は、コットの横幅に合ったサイズを選ぶことが大切です。マットが大きすぎるとはみ出してしまい、小さすぎると体がコットに直接触れてしまいます。
枕があると寝心地が段違い
意外と忘れがちなのが枕です。キャンプ用の枕は、空気で膨らませるタイプや、衣類を入れて使うタイプなどがあります。
枕がないと、首や肩が痛くなって、せっかくのコットの快適さが半減してしまいます。コンパクトに収納できる枕を一つ持っておくと、キャンプでの睡眠の質が大幅に向上します。
キャリーカートで運搬が楽になる
重いコットを運ぶ時は、キャリーカートがあると非常に便利です。車からサイトまでの距離がある場合や、複数のコットを運ぶ場合には特に役立ちます。
折りたたみ式のキャリーカートなら、使わない時はコンパクトに収納できます。コット以外のキャンプ道具も一度に運べるので、往復の回数を減らせて効率的です。
おすすめコット3選とリンク
ここまでコットの選び方について詳しく説明してきましたが、最後に私が実際に使って良かったと感じたおすすめのコットを3つご紹介します。
1位 WAQ 2WAYフォールディングコット
WAQの2WAYフォールディングコットは、ハイスタイルとロースタイルを切り替えられる万能タイプです。重量は約3.2キロと軽量で、持ち運びやすさと使いやすさのバランスが絶妙です。
生地は600デニールのポリエステルを使用していて、張りがしっかりしています。横幅も65センチあるので、窮屈さを感じません。組み立ても比較的簡単で、慣れれば5分程度で設営できます。
耐荷重は150キロと十分な強度があります。価格は1万3千円前後と、コストパフォーマンスに優れた一台です。初めてコットを購入する方に特におすすめできます。
2位 DOD バッグインベッド
DODのバッグインベッドは、寝心地の良さに定評があるローコットです。重量は2.6キロと軽量で、収納サイズもコンパクトなので、ソロキャンプやバイクキャンプに最適です。
横幅は71センチとワイド設計で、寝返りも楽にできます。生地の張りも適度にあって、体が沈み込みすぎることもありません。軋み音も小さく、静かに眠れます。
組み立ては組み立て式で、7本の脚部を取り付ける必要があります。最初は少し時間がかかりますが、慣れればスムーズに組み立てられます。価格は1万円前後と、この性能でこの価格は非常にお得です。
3位 ヘリノックス コットワン コンバーチブル
ヘリノックスのコットワン コンバーチブルは、高級モデルですが、その価値は十分にあります。重量はわずか2.2キロと超軽量で、組み立ても非常に簡単です。
フレームにはDAC社製のアルミポールを使用していて、軽くて頑丈です。生地の張りも絶妙で、寝心地は抜群です。専用の脚を追加することで、ハイスタイルにも変更できる拡張性も魅力です。
コットを使った快適なキャンプライフを
ここまで、コットの選び方について詳しく解説してきました。ハイコットとローコットの違い、寝心地を左右するポイント、組み立てやすさ、重量とサイズ、素材と耐久性など、チェックすべきポイントはたくさんあります。
重要なのは、自分のキャンプスタイルに合ったコットを選ぶことです。ソロキャンプやバイクキャンプなら軽量コンパクトなローコット、ファミリーキャンプやオートキャンプなら快適性重視のハイコット、迷ったら2WAYコットという選び方がおすすめです。
コットは決して安い買い物ではありませんが、一度購入すれば何年も使い続けられます。価格だけで選ぶのではなく、自分が重視するポイントをしっかり考えて、納得のいくコットを選びましょう。
実際にコットを使ってみると、地面で寝ていた時とは比べものにならないほど快適に眠れることに驚くはずです。朝まで熟睡できると、翌日のキャンプもより楽しめます。コットは、キャンプの質を大きく向上させてくれる投資価値の高いアイテムです。
この記事が、あなたにぴったりのコット選びの参考になれば嬉しいです。快適なコットと一緒に、素敵なキャンプライフを楽しんでください。
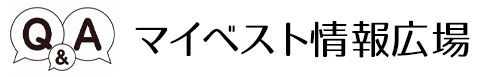


組み立て式の中には、レバー式で脚部を取り付けられるモデルもあります。レバーを使うとてこの原理で力を軽減できるので、女性でも比較的楽に組み立てられます。組み立て式を選ぶなら、このレバー式がおすすめです。